まず前提として、早大本庄の合格難度は年々上がっています。
2021年辺りから2025年までの難度の上がり方がものすごく、毎年偏差値で2ポイントずつくらい上昇しているイメージです。
もともとは、「ちょっと遠いけどその分受かりやすいよ。原則100%早稲田大学に行けるし」といった感じで、いわゆる「オイシイ学校」として生徒に勧める学校でした。
いまは、決してそういうレベルではありません。
特に女子の早大本庄の合格難度は、女子最難関の慶應女子高と並びます。
実際、私の教え子でも、慶女に合格して本庄に落ちてしまった子は2名います(念のため、私の教え子で本庄に合格した子も数えきれないくらいいることは付記しておきます)。2人とも慶女第一志望の子だったので、本庄の対策はそこまでしっかりしていなかったというのもありますが、それでも少し前なら考えられないようなことでした。
なぜ早大本庄がそんなに人気かというと、やはり「共学であること」「通っている生徒・保護者の満足度が非常に高いこと」が挙げられると思います。
遠いですが、東京都から通っている生徒にも人気のようです。早大に進学できる・校舎が超綺麗なのはもちろんのこと、「自然に囲まれた環境が良い」とか、「生徒たちの雰囲気が良い」とか、そういった話も聞きます。
ただ、2025年でほとんど慶女に並び、さすがにその人気は天井に到達したのではないかと思われます。また、2026年度入試から、男女の定員比が変わるという発表があります(男子100名・女子70名→男子95名・女子95名)。したがって、2026年度入試の入学難度※は2025年度とさほど変わらないか、女子にとっては少しだけ易しくなると予想しています。
※合格難度の話であって、入試問題の難度は上がるかもしれません。特に英国。
今回の記事では、そんな大人気の早大本庄の入試の傾向と対策を書いてみます。
早大本庄の入試傾向と対策
ボーダーライン(合格最低点)
早大本庄の入試に関しては、(数学の)難度が近年ぐんぐん上昇しており、ボーダーラインが読みづらいのが現状です。
2022年以前であれば、3科目計210点くらい必要と思われましたが、2024年・2025年の入試の合格最低点は190点前後かと思われます。
2025年の合格最低点の内訳としては、
- 数学50~55点
- 英語65~70点
- 国語70~75点
というイメージを持っていただければと思います。
「得意2・苦手1」「得意1・ふつう2」を目指す
「得意2・苦手1」というのは、たとえば「英国が得意で数学は苦手」という状態です。たとえば私の過去の生徒では、「英国80点・数学40点」という得点で合格した子がいました。得意科目が2つあれば、苦手科目1つをカバーすることができます。
大事なことは、「得意1・苦手2」という状況のまま入試に突入しないということです。
早大本庄を目指し、最終的には合格を勝ち取っていくような生徒でも、やはり中2くらいまでは「得意1・苦手2」になっている生徒が多いです。そこからいかにして「得意2」の勝ちパターンに持っていくかが合格率を高めるうえでの大きなポイントになります。
各科目ごとの傾向と対策
英語
近年は、「大問1が空所補充(文法・語法・語彙)・大問2が説明文・大問3が対話文」という形式に落ち着いています。
大問1に関しては、いわゆる「文法問題」(時制などの問題)が3問、連語や単語に関する知識が7問というイメージです。連語の勉強は重点的にやっておく必要があります。大問1は基本的なものが多いので、しっかりと高得点を狙いたいところです。英検準2級プラスレベルの語彙までは確実に押さえておきたいです。
英訳や和訳はありますが、量的には少ないです。リスニングはありません。
対話文は、クセのある人物が登場したりするので、常識や思い込みに捉われずに、書いてある英文のニュアンスをそのまま読み取れる力が大事になります。
大問2の説明文で段落ごとの内容一致の問題が出ますが、文章全体が読めていたうえでも、なかなか際どい選択肢が出ています。英語の先生でも答えが割れることがあります。
なので、読解に関しては、精度高く英語を理解する力をつけることが大切です。「単語・熟語力」と、「文法に基づく読解力」を身につけることが重要です。
数学
年を追うごとに難しくなっています。
2020年までの問題は全体的に解きやすかったです。2021年~2023年あたりは、「受験生にとっては解きづらい問題がちらほらある」というくらいでした。2024年・2025年は、その解きづらい問題の割合がさらに増えていた印象です。
2025年の数学であれば、数学が得意な生徒でも70点。他科目でカバーできる生徒であれば、50点も取れれば十分だったと思われます。(40点でも可能性ありというイメージ)
平方根や二次式を含む高い計算力が求められます。
また、その場でルールに従って考える問題がよく出ます。パターン暗記で乗り切ろうとすると、本庄の数学はやや苦しいですから、普段からすぐに解答を見ずに、自分で手を動かして考える知的体力を鍛えておく必要があります。
国語
近年は大問2題構成で固定されています。
漢字や語句の知識問題、選択問題、抜き出し問題、記述問題と、幅広くバランスよく出題されています。
読解問題の解答根拠の探し方に特徴があり、それを踏まえて解くのがとても有効です。(入塾者には詳しく説明しています)
本庄の国語はあまり難しすぎるような奇問もなく、解きやすいです。国語は、一度得意になってしまえばあまり力の衰えない教科なので、早めにしっかりと得点力をつけておきたいところです。
平均点が高めなので、国語が壊滅的だとかなり足を引っ張ってしまう可能性がありますから、国語が苦手な場合にはしっかりと対策が必要です。
夏~秋に過去問を解いた場合の得点率
夏~秋(8月、9月、10月、11月)にかけて、初めて早大本庄の入試問題を解く生徒が多いと思います。過去の合格した生徒の例でいえば、ほとんどの場合、夏や秋の時点で合格点は取れていません。入試本番では余裕を持って合格していった生徒でさえ、です。
最終的に合格する生徒でも、9月、10月に数学の過去問を解いて、30点とか40点という点数を取ってしまうことはザラにあります。そこからどうしたら伸ばせるのか、というのは、…企業秘密です(笑)
一番大事なこと
私見ですが、高校入試は、中学入試や大学入試と比べて、最も努力が実を結びやすいと思っています。
限られた学習範囲の中で、高校ごとに毎年同じような傾向・形式で入試問題を出題しているので、そうした学校ごとの傾向を把握している教師と一緒に、そこに絞って対策をすれば何とかなることは多いです。
私は過去、中学受験でマーチレベルの学校に落ちてしまった子を、高校受験で早慶附属高校に合格させたこともたくさんあります。「過度に悲観的や楽観的にならずに、やるべきことを淡々とこなしていく」ことが、そうした逆転合格を引き寄せるカギとなります。
もちろん、だれしもモチベーションを保つのが難しかったり、心が折れそうになる時期もあります。そういうときに、周りの大人たちがいかに伴走して支えてあげられるか、というのもまた重要です。
本気で早大本庄高に合格したい方。ぜひコリスの個別指導で一緒に走り抜け、早大本庄高校の合格をつかみ取りましょう。


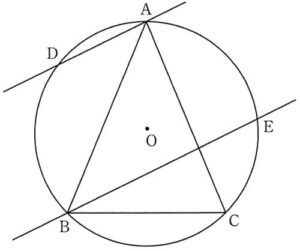
コメント